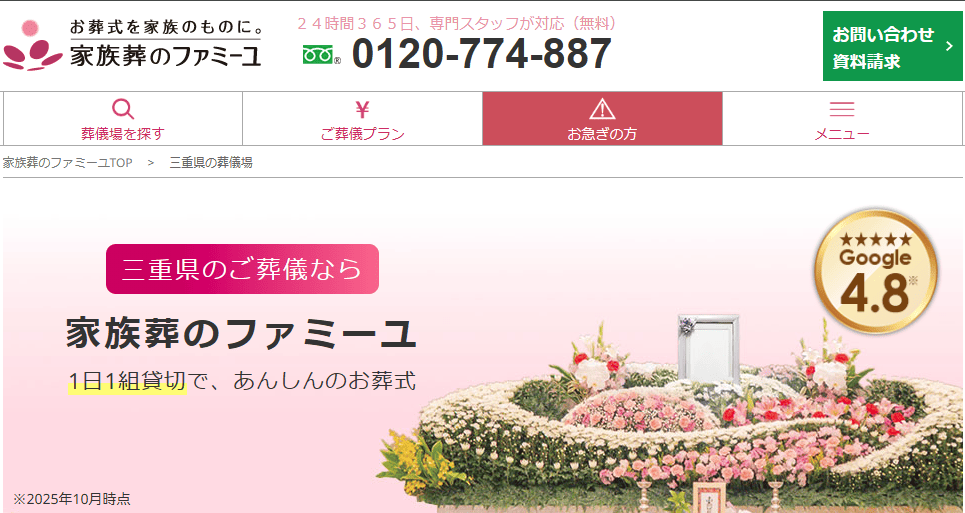突然の訃報を正しく伝えるために!連絡の仕方と伝えるべき内容とは
 大切な人が亡くなった際、遺族や関係者には訃報を速やかに伝える必要があります。しかし、突然のことで動揺している中、誰にどう連絡すればよいのか迷う人も多いのではないでしょうか。本記事では、訃報を伝える際の基本的なマナーや電話やメールでの適切な伝え方、盛り込むべき内容についてご紹介します。
大切な人が亡くなった際、遺族や関係者には訃報を速やかに伝える必要があります。しかし、突然のことで動揺している中、誰にどう連絡すればよいのか迷う人も多いのではないでしょうか。本記事では、訃報を伝える際の基本的なマナーや電話やメールでの適切な伝え方、盛り込むべき内容についてご紹介します。
訃報連絡とは?誰に知らせるべきか
身近な人が亡くなった際には、関係者へ速やかに訃報を伝える必要があります。しかし、いざというときに「訃報連絡とは何か」「誰に連絡すればよいのか」と迷ってしまうこともあるでしょう。ここでは、訃報連絡の基本と、連絡すべき相手についてご紹介します。
訃報とは亡くなったことを伝える連絡のこと
訃報(ふほう)とは、身内や関係者などに「亡くなった」という事実を知らせることを指します。多くの場合は電話やメールなどで行われ、内容は簡潔かつ丁寧に伝えるのが一般的です。
訃報は突然の知らせであることが多いため、聞いた側が冷静に対応できるよう、配慮のある伝え方が求められます。形式よりも、相手に必要な情報がきちんと伝わることが大切です。
訃報は葬儀に来てほしい人へ伝えるのが基本
訃報連絡は、基本的に葬儀や通夜に参列してほしい人を対象に行います。家族や親戚、故人の親しい友人や勤務先の関係者などが該当します。
また、訃報を伝えるかどうかは、遺族の意向にも左右されるため、あらかじめ家族間で方針を確認しておくことも大切です。故人との関係性や距離感を踏まえ、誰に伝えるべきかを判断しましょう。
訃報の連絡方法はどうすればいい?
連絡方法にはいくつかの手段があり、相手との関係性や状況に応じて使い分けることが求められます。ここでは、訃報を伝える際の主な連絡方法についてご紹介します。
電話での連絡
訃報を伝える手段としてもっとも一般的なのが電話です。相手の反応を直接確認できるため、親族や親しい関係の人には電話で連絡するのが望ましいとされています。
時間帯にも配慮し、早朝や深夜は避けるのがマナーです。また、突然の連絡に驚く人もいるため、落ち着いた口調で伝えるよう心がけましょう。
メールやLINEなどのメッセージツール
電話が難しい場合や相手との関係性によっては、メールやLINEなどのメッセージツールを使って訃報を伝えることもあります。とくに連絡を一斉に行いたい場合や仕事関係者などに形式的に伝える際に適しています。
ただし、重要な連絡であることを意識し、言葉選びや文面には十分な配慮が必要です。
手紙での連絡
遠方の親戚や日常的に連絡を取っていない人への訃報は、手紙で伝えることもあります。すぐに連絡する必要がない場合や葬儀後に改めて報告する際などに用いられます。
手紙では丁寧な文章が求められ、形式や文例に沿って書くのが一般的です。心を込めて、相手に誠意が伝わるよう意識しましょう。
訃報連絡で伝えるべき内容とは
訃報連絡をする際は、限られた時間で必要な情報を正確かつ丁寧に伝えることが大切です。以下では、訃報連絡の際に伝えるべき基本的な内容や状況に応じた連絡のポイントをご紹介します。
伝えるべき基本情報
訃報を伝える際には、最初に連絡者と故人の関係性を明確にし、故人の氏名・亡くなった日時・死因・緊急連絡先を伝えるのが基本です。これらの情報は相手が状況を理解し、必要な対応をとるために重要な要素です。
電話の場合はとくに、一度に多くの情報を伝えることになるため、メモなどで事前に整理しておくとスムーズに連絡できます。
訃報のみを伝える場合の注意点
葬儀の詳細が未定の場合など、まずは訃報だけを伝えるケースでは、通夜や葬儀に関する連絡は後ほど改めて行うのが一般的です。ただし、すぐに駆けつけてもらいたい場合には、病院や安置場所、自宅など、来てほしい場所を明確に伝えてください。
その際、相手の移動時間も考慮し、無理のない時間帯での案内を心がけましょう。
葬儀の詳細も伝える場合
通夜や葬儀の日程がすでに決まっている場合は、訃報とあわせてその詳細も伝えます。具体的には「誰が」「いつ」亡くなったのかに加えて、通夜と葬儀の日時・場所・形式(仏式・神式など)、喪主の氏名と故人との関係などを伝えます。
参列を希望する人にとって必要な情報を過不足なく届けることが、円滑な対応につながります。
訃報を連絡する順番と伝える範囲について
訃報を伝える際には、連絡する相手の順番が大切です。まずは家族や親族へ知らせるのが基本で、おおむね三親等までの範囲を目安にしましょう。三親等とは祖父母や兄弟、甥姪などを含み、近しい血縁者に訃報を速やかに伝えることで、遺族の連携もスムーズになります。
次に、故人の友人や知人、会社関係者へ連絡を行います。これらは故人と日常的に関わりのあった人々で、葬儀への参列やお別れの機会を共有するために欠かせません。
最後に、遺族の関係者や親しいご近所の人など、そのほかの関係者に知らせるのが一般的です。連絡の順番を意識することで、混乱を避け、訃報を受け取る側も適切に対応しやすくなります。
まとめ
訃報連絡は、故人の訃報を適切な相手に速やかに伝える大切な役割です。まず、誰に知らせるべきかを確認し、家族や親族をはじめ、故人の友人や関係者に順序立てて連絡します。連絡方法は電話やメール、手紙など状況に応じて使い分けることが重要です。また、伝えるべき内容は故人の氏名や死亡日時、連絡先など必要最低限の情報を押さえましょう。訃報を正しく伝えることで、関係者が落ち着いて対応でき、葬儀の準備や弔問もスムーズに進められます。
-
 引用元:https://saihokaku.jp/
引用元:https://saihokaku.jp/
斎奉閣(さいほうかく)は、三重県内に23の会館を展開し、近隣の会館を安心してご利用いただける体制を整えています。50名以上の厚生労働省認定の葬儀ディレクターや三重県初の上級グリーフケア士が在籍し、質の高い葬儀サービスをご提供しています。初めての葬儀で不安な方も、親身にサポートしてくれるのでまずは相談してみてはいかがでしょうか。