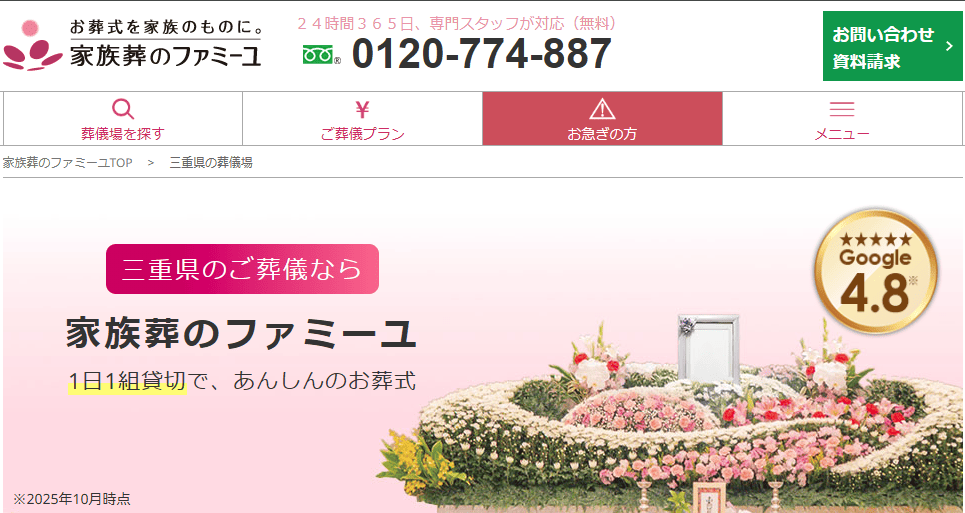なぜ人間は葬儀をするのか?変わりゆく儀礼とその意義を解説

近年、葬儀の形態や意味が大きく変容しています。とくに家族葬や直葬といった小規模な葬儀が普及し、死との向き合い方が個人化してきました。しかし、葬儀には物理的、文化的、社会的な意味があり、その重要性は変わりません。この記事では、葬儀の変遷とその役割について解説します。
葬儀の変遷と小規模化
1990年代から現在にかけて、葬儀の小規模化が進行しています。
その代表的な例が家族葬であり、従来の密葬に似た形式を持ちながら、より温かみのある名称として広く普及しました。家族葬は、亡くなった人を家族や親しい人だけで見送れるため、近年では非常に人気があります。
これに加え、一日葬儀や、儀礼を最小限に抑えた直葬など、新しい形式も登場しました。とくに直葬は、費用や時間を大幅に削減し、儀礼を省略することで個人や家族に負担をかけない形が増加しています。さらに、近年の孤独死の増加も、葬儀の個人化を後押ししています。
現在では多くの人が病院で死を迎えるため、死のプロセスは病院の医療スタッフや葬儀業者といった外部の専門家に依存することが一般的です。このような状況のなかで、葬儀において親族が主導する役割が縮小し、葬儀そのものの意義を再考する機運が高まっています。
しかし、人類の歴史を振り返ると、葬儀という儀礼は人間が死と向き合うために欠かせないものであり、その役割は変わりません。
葬儀の意義とは
葬儀には、大きく分けて三つの重要な役割があります。
第一に、物理的な変換です。これは、亡くなった人の遺体を適切に処理することであり、土葬や火葬といった方法を用いて遺体を埋葬または焼却するプロセスを指します。この物理的な変換は、人間が死後も他者に衛生的な問題を引き起こさないために必要不可欠です。
第二に、文化的な変換があります。これは、死者が新たな世界で生き続けるという文化的な意味づけを行い、遺族や社会全体がその死を受け入れるためのプロセスです。
たとえば「おじいちゃんはお星さまになった」といった表現を通じて、死者が永遠に存在し続けるというイメージが形成され、悲しみを和らげる役割を果たします。この文化的な変換により、死は単なる終わりではなく、新たな形での存在が意味づけられます。
第三に、社会的な変換です。これは、亡くなった人が社会で果たしていた役割を再分配し、遺族や友人、同僚が新たな役割を担うことを意味します。たとえば、葬儀で喪主が選ばれることで、家族内でのリーダーシップが引き継がれたり、故人の社会的地位が他の人々に引き継がれたりします。
このように、葬儀は死者を送り出すだけでなく、社会全体の秩序を維持するための重要な儀礼として機能しているのです。
葬儀の歴史と葬列の変遷
かつて日本の葬儀は、葬列という形式で行われていました。
葬列とは、遺体を家から墓地に運ぶ行為で、これは単なる移動ではなく、あの世へと死者を送り出す儀礼的な意味が込められています。遺族や参列者が一体となり、故人の最後の旅路を見守るという共同体の強い結びつきを象徴する重要な行事だったのです。
この葬列を通じて、参列者全員が死者を送り出すという共通体験を持つことで、死を受け入れるプロセスが成り立っていました。葬列にはさまざまな儀礼道具が必要であり、それを提供する専門の葬具業者も存在していました。
江戸時代から葬列のための「龕師(かんし)」と呼ばれる葬具業者が現れ、葬具のレンタルや販売が行われるようになったのです。葬列の規模や使用する道具の豪華さは、そのまま葬儀のランクを表し、故人の社会的な地位や家族の財力を示すものとなっていました。
とくに明治時代には、葬列を組むための専門の人足が雇われることもあり、葬列が家の名誉や社会的ステータスを示す重要な要素として機能しました。しかし、近代に入ると交通事情の変化や、社会全体の合理化の影響を受けて、葬列は徐々に廃止される方向に向かったのです。
とくに都市部では、街中を葬列が通ることが交通の妨げとなり、次第に葬列は行われなくなっていきます。こうして、現代の主流である告別式が誕生し、葬列に代わる葬儀の形式となりました。
告別式の成立と普及
告別式は、宗教的な儀礼を排除し、死者との別れに重きを置く新しい儀礼として、明治時代に初めて登場しました。
最初の告別式は、無神論者であった思想家・中江兆民の葬儀で行われたもので、宗教的な要素を排除し、死者を弔うという形での別れが強調されました。これがきっかけとなり、告別式は、とくに都市部の知識層を中心に広がっていきます。
告別式の普及には、都市化や合理化の影響が大きく関与しています。葬列に比べて場所や時間に縛られず、交通に影響を与えることもないため、都市部では告別式が次第に一般的な形式となっていきました。
昭和初期には、地方にも告別式の文化が広がり、次第に葬儀全体の主流を占めるようになります。告別式は、葬列のように大規模な移動を伴うことなく、故人との別れをより簡便に、そして社会的な意味を持つ儀式として行われるようになり、葬儀において重要な役割を果たすようになりました。
現代の葬儀と個人化
1990年代以降、少子化や家族構成の変化に伴い、葬儀の形態はさらに変化しています。
家族葬や直葬が増え、葬儀が持つ社会的意義は縮小しています。とくに、個人化が進む現代では、死者との関わりが希薄になりつつあります。家族葬の増加により、参列者は限られ、死者と向き合う機会が少なくなりました。
このような状況では、他者の死を通じて自分の死を考えることが難しくなっています。死に対する共通体験が失われ、葬儀の持つ社会的な意義が見直されるべき時代に来ていると言えるでしょう。
死者を忘れないために
葬儀のもうひとつの役割は、死者を緩やかに記憶に留めることです。
人々は、死後に自分が忘れ去られることを恐れますが、遺族は故人のことをいつまでも覚えていられないため、葬儀や年忌法要が役割を果たします。これにより、死者の存在はゆるやかに消えていくのです。
まとめ
葬儀は、単に遺体を処理するだけでなく、死者と生者の関係を見つめ直し、社会や文化のなかで死を意味づける重要な儀礼です。現代の葬儀は個人化が進んでいますが、死を通じた共通体験が持つ意義は失われていません。これからの時代、葬儀のあり方を再考し、より深い意味を持つ儀礼としての役割を見つけていくことが求められるでしょう。
-
 引用元:https://saihokaku.jp/
引用元:https://saihokaku.jp/
斎奉閣(さいほうかく)は、三重県内に23の会館を展開し、近隣の会館を安心してご利用いただける体制を整えています。50名以上の厚生労働省認定の葬儀ディレクターや三重県初の上級グリーフケア士が在籍し、質の高い葬儀サービスをご提供しています。初めての葬儀で不安な方も、親身にサポートしてくれるのでまずは相談してみてはいかがでしょうか。